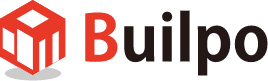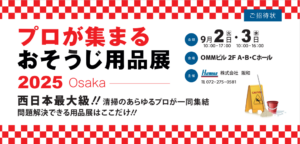「建設DXって何?」「建設業界のデジタル化は私たちにどんなメリットをもたらすの?」そう思う方もいるのではないでしょうか。
建設DXとは、最新のデジタル技術を活用して建設業界の生産性を高め、作業の効率化を実現するプロセスです。
今記事では、建設DXがもたらす革新的な変化とその具体的な取り組み方法について詳しくご紹介していきたいと思います。
建設業界におけるデジタル変革(建設DX)の必要性
建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(建設DX)は、業務効率化や課題解決のために、AIやデジタル技術の導入を進める取り組みを指します。
建設業界は、長らくアナログの手法に依存してきましたが、現代の社会変化に伴う課題に直面しています。
建設DXの求められる背景
建設業界でDXが求められる背景には、主に2つの要因があります。
- 新型コロナウイルスの影響: コロナ禍により、非対面、非接触の業務方法が求められるようになりました。しかし、建設業界はオンラインでの業務に対応する環境が整っていないため、業務継続における課題が顕在化しました。
- 少子高齢化による人手不足: 日本の少子高齢化は、労働人口の減少を招き、建設業界においても人手不足が深刻な問題となっています。1990年には総人口の62%を占めていた労働世代が、2040年には50%まで減少すると予測されています。参考文献:経済産業省
建設DXとは何か
建設DXは、業務のデジタル化を通じて、建設業界特有の課題を解決しようとする取り組みです。
具体的には、AIやディープラーニングを活用して、人手不足や技術の継承などの問題に対応します。
しかし、建設業界には古くからの慣習が根強く残っており、図面や資料をアナログで管理するなどの旧来の方法がまだ多く見られます。
このため、建設DXの推進には、こうした慣習からの脱却が不可欠です。
建設DXは、業務効率化や技術継承、人手不足の解決など、多くの課題に対処するための重要なステップであり、建設業界におけるデジタル技術の積極的な導入が鍵となります。
建設業界が直面する課題
建設業界におけるDXの重要性を理解するためには、まずこの業界が直面している主要な課題を把握することが必要です。
労働力の減少と技術継承の問題
建設業界は深刻な労働力不足に直面しています。国土交通省の報告によると、1997年には約685万人だった建設業の就業者数が、2020年には約492万人まで減少しました。
これは、総人口に占める労働年齢層の減少による影響が大きいと考えられます。
高齢化の進行
さらに、建設業界の労働者は高齢化が進んでいます。2020年のデータでは、55歳以上の労働者が全体の36%を占め、若年層はわずか12%に留まっています。
この状況は、伝統的な建築技術の継承が困難になる可能性を示しています。
過酷な労働環境
建設業界では、長時間労働が常態化しています。
2020年のデータによると、年間実労働時間は全産業平均より約20%多い1985時間にものぼり、年間出勤日数も全産業平均より32日多い244日でした。
これにより、働き方改革の必要性が高まっています。
生産性の低さ
建設ハンドブック2021によれば、建設業界の2019年の付加価値労働生産性は2872.9円/人・時間で、全産業平均の約半分にとどまっています。
これは、業務の標準化が難しい業界特性や、適切な人材配置が難しい状況などが要因です。
非効率な業務
建設業界では、手作業が多く、また各現場の環境が異なるために業務の標準化が困難です。
これが生産性の低さにつながっています。
対面主義の問題
建設業界では、現場に赴く必要があるなどの理由でテレワークが導入されにくく、総務省の発表によると2020年のテレワーク実施率は15.7%と低い数字を示しています。
これは、コロナ禍での働き方の変革が求められる中、建設業界が直面している課題の一つです。
建設DXによる業界変革とそのメリット
建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の導入には、多くのメリットがあります。
ここでは、その主な利点を詳しく見ていきましょう。
業務プロセスの効率化
建設DXにより、3Dモデリングなどのデジタルツールを活用して、建設現場の作業計画や打ち合わせがオンラインで行えるようになります。
これにより、現場までの移動時間を削減し、他の業務に費やす時間を増やすことが可能です。
一元管理による情報共有の効率化
デジタル技術を駆使することで、設計図面や工程表などの情報を一元管理し、関係者間での情報共有が迅速かつ効率的に行えるようになります。
省人化と作業の効率化
デジタル技術の導入により、建設機械を遠隔操作できるようになり、作業に必要な人員を削減し、効率的な作業運用が可能になります。
デジタル化による作業の効率化は、限られた労働力をより効果的に活用することを可能にし、人材不足の問題を軽減します。
技術継承の促進
建設DXの進展により、熟練工の技術やノウハウをデジタル化し、若手技術者への技術継承が容易になります。
これにより、伝統的な建築技法や専門知識の維持・発展が期待できます。
建設業界の主なデジタル技術
建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、さまざまなデジタル技術を駆使して進行しています。
ここでは、建設DXで用いられる主要なデジタル技術を見てみましょう。
人間の知能を模倣するAI技術は、建設DXの核となる要素です。
例えば、現場写真の分析による進捗管理や安全設計の自動評価、職人技のデータ化など、AIを活用した革新的な取り組みが進行中です。
AI
建設業界におけるAIの導入は、業務の安全性と生産性の向上に革命をもたらしています。
AI技術は、画像認識やセンサー利用を通じて、危険な作業の自動化や、無人での建設機械操作を可能にしています。
例えば、AI搭載ドローンや自律制御された建設機械を利用することで、リスクの高い現場作業を安全に代行させることができます。
さらに、第四次AIブームとして注目を集める今、AIは建設業界においても更なる進化を遂げています。
二次元CADから三次元モデルへの変換や、無人建機の自律作業化など、研究が進められています。
また、生成型AI技術を活用した施工管理や経営管理への応用も始まっており、建設業界の効率化と革新を促進しています。
これらの技術の発展により、建設業界は属人化を防ぎ、安全かつ効率的な作業環境の実現に向けた大きな一歩を踏み出しています。
ドローン
建設業界におけるドローン技術の進化
ドローン活用による作業の効率化と安全性の向上
建設業界では、AIとセンサー技術を搭載したドローンが、高所や難アクセス地点での点検や測量を安全かつ迅速に実行し、大幅な作業効率化を実現しています。
高精度なデータ収集により、作業の精度も向上し、リスクの低減とコスト削減に寄与しています。
建設現場における新たな技術革新の波
ドローンとAIの融合は、遠隔からの建設現場管理を可能にし、現場の進捗管理や安全監視をリアルタイムで行えるようになりました。
収集したデータは未来のプロジェクト計画や品質改善の重要な情報源となり、建設業界の働き方改革に貢献しています。
これらの技術進化は、建設業界に新たな展望を開き、より安全で効率的な作業環境を実現しています。
クラウドサービス
建設業界に革命をもたらすクラウドサービスの活用
建設業界では、膨大な情報共有と文書管理が課題となっていますが、クラウドサービスの導入により、これらの問題が効率的に解決されています。
政府のIT導入補助金を利用し、多くの企業がクラウドサービスを導入。この技術は、施工管理、情報共有、文書の管理をデジタル化し、業務プロセスの効率化を実現しています。
クラウドサービスによる働き方改革
クラウドサービスを活用することで、施工現場とオフィス間のリアルタイムな情報共有が可能になり、作業指示や進捗確認がどこからでも行えるようになります。
これにより、作業の効率化だけでなく、働き方の改善が期待できます。クラウドサービスのさらなる活用は、建設業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させ、業務プロセスの最適化に貢献しています。
LiDAR技術で測量
建設業界では、ドローンとLiDAR(Light Detection and Ranging)技術の組み合わせにより、これまで手の届かなかった高精度な地形測定が可能になっています。
LiDARセンサーを搭載したドローンを用いることで、山間部や森林地帯など視覚的に把握が難しい地表も正確にデータ化することができます。
この技術により、精密な地形データの収集が容易になるだけでなく、土木工事やインフラの保守点検においても、人の手が届きにくい場所の情報をリスクなく収集できるようになりました。
LiDAR技術の建設業界への応用拡大
LiDAR技術は、その高い測定精度と広範囲をカバーできる特性から、建設業界における様々なシナリオでの活用が期待されています。
例えば、トンネル建設や斜面の崩壊リスク分析、覆工コンクリートの品質評価など、従来は人間の目での確認が主であった領域にLiDARが導入されることで、より精確かつ迅速なデータ分析が可能になります。
また、LiDAR技術を活用した3Dモデリングは、事前の計画段階でのシミュレーションやリスク予測にも有効で、建設プロジェクトの成功率を高め、工期の短縮やコスト削減にも寄与します。
これらの技術進歩は、建設業界における生産性の向上だけでなく、作業の安全性向上にも大きく貢献しています。
IoT
建設業界におけるIoTの導入は、安全性の向上や労働時間の削減など、労働環境を大きく改善しています。
特に、センサー技術の利用によって、建機や人員の位置情報をリアルタイムで把握し、事故のリスクを減少させることが可能になりました。
また、ドローンや遠隔監視システムの導入により、危険な現場の作業を安全な場所から行えるようになり、作業効率の向上にもつながっています。
IoTによる業務の効率化とコスト削減
IoTの導入は、建設現場の業務効率化とコスト削減にも大きな影響を与えています。
データの一元管理や遠隔での現場管理が可能になることで、不要な人員配置や資材の無駄を削減し、生産性の向上を実現しています。
また、熟練技術のデジタル化により、技術の継承問題を解決し、長期的な業界の発展を支える基盤を構築しています。
IoTは、建設業界における新たな働き方やビジネスモデルの確立を促進する重要な技術として、ますますその重要性が高まっています。
5G
5G通信技術の導入により、建設業界ではこれまでにない速度と効率性が実現しています。
高速・大容量の特徴を活かし、現場からの大量のデータ送信や、遠隔地からの3D映像共有がスムーズに行われるようになりました。
これにより、建設現場のリアルタイムな監視や進捗管理が可能となり、作業効率の大幅な向上が見込まれます。
5Gを活用した未来の建設現場
5Gの「高信頼・低遅延」特性は、建設機械の遠隔操作に革命をもたらします。
通信の遅延を最小限に抑えることで、遠隔地からでも正確な操作が可能になり、人手不足が問題となる建設業界に新たな解決策を提供します。
また、多接続により、現場に設置された多数のセンサーやカメラからの情報を一元管理することができ、安全性の向上やリスク管理の効率化が期待されます。
これらの技術進化は、建設業界における生産性の向上だけでなく、働き方改革にも大きく貢献するでしょう。
BIM/CIM
建設業界では、国土交通省が推進するBIM/CIM技術の導入により、設計から施工、維持管理に至るまでのプロセスが劇的に変化しています。
従来の2次元図面に依存した作業から脱却し、3次元モデルを用いることで、干渉チェックや維持管理を初期段階で考慮した設計が可能になっています。
この3次元モデルは属性情報を持つため、特定の工事項目に対する交換性の検討など、より詳細な分析が行えるようになりました。
これにより、建設プロジェクトの生産性と効率性が大幅に向上し、質の高い建築物の提供が期待されています。
ERP
建設業界は、デジタル変革(DX)を通じて労働力不足や生産性の課題に対応し、さらなる業務効率化を目指しています。
経済産業省が指摘する「2025年の崖」を克服し、国際競争力を維持するため、各企業はDXを積極的に推進。
この流れの中で、ERP(Enterprise Resource Planning)システムの導入が、建設業界でも注目を集めています。
ERPシステムは、企業の基幹業務を一元的に管理し、データの一貫性を保ちながら業務プロセスを最適化します。
特に、建設業に特化したERPシステムは、工事の進捗管理や複雑な会計処理に対応し、プロジェクトごとの財務管理を効率化することで、業界特有の課題解決に貢献しています。
これにより、建設現場の自動化推進、バックオフィス業務の統合、さらには働き方改革にも寄与し、建設業界の持続可能な発展を支えています。
3Dプリンター
建設現場における3Dプリンティング技術の革命
生産性とデザインの革新
建設業界に3Dプリンティング技術が導入されることで、これまでの建築プロセスは大きく変わります。
従来の建築作業に必要だった時間と労力が大幅に削減され、より複雑で革新的なデザインの実現が可能になります。
材料の無駄遣いも減少し、結果としてコストダウンと環境負荷の軽減に繋がります。
施工スピードと安全性の向上
3Dプリンティング技術は、建設現場の安全性向上にも寄与します。
高所や危険な場所での作業が減少し、人的リスクが軽減される一方で、建築物の施工スピードが向上します。
さらに、AIとの融合により、デザインから施工までの一連の流れがデジタルで連携し、高品質な建築物を効率良く提供できるようになります。
建設業界におけるデジタル化の推進
日本政府は、i-Constructionを通じて、建設業界におけるデジタル化を推進しています。
参考文献:i-Construction ~建設現場の生産性革命~
この取り組みは、ICT技術の利用と規格の標準化に重点を置いています。
国土交通省の方針として、BIM/CIMの原則が公共事業において広く適用されるようになっています。
これにより、建設プロジェクトの効率化と品質向上が期待されています。
建設DX成功のためのガイドライン
建設業界におけるデジタル変革の取り組みを成功に導くためには、現場の従業員の声に耳を傾けることが重要です。
彼らの意見や要望を反映することで、作業の効率化と快適性を高めることが可能になります。
また、突如としてのデジタル化には抵抗が予想されるため、DXの重要性や利益を事前に説明し、理解を深めることが必要です。
自社のニーズに応じたDX戦略の策定
自社の現状とニーズを正確に把握し、その上で建設DXの目標と戦略を設定することが成功へのカギとなります。
不明確な目標では、従業員のやる気を損ねたり、無駄な取り組みに時間を費やすことになりかねません。
従業員全員が共通の目的を理解し、一丸となってDXに取り組めるように計画を立てましょう。
自社に適したデジタルツールの選定
多様なデジタル技術の中から、自社の特定の課題を解決できるツールを選択することが、DXの成功への鍵です。
ただし、導入した技術が使いにくかったり、社内のニーズに合っていなかったりすると、DXの推進が困難になることがあります。
従業員の使いやすさを考慮し、最適なツール選定に努めましょう。
自社の特性に合わせたDX化の実現
建設業界では、他社の成功事例を真似るだけでは、自社にとっての最適なDX化は実現しない可能性が高いです。
各社の現場環境やバックオフィスの業務は異なるため、自社固有の課題に基づいたDX化が求められます。
自社の特性を理解し、それに沿ったDX戦略を立てることが重要です。
競争優位を意識したDX展開
他社との差別化を図ることは、建設DXの成功において不可欠です。
例えば、技術面だけでなく、システムの連携や作業のしやすさで競合他社との差をつけることが、プロジェクトの受注や顧客満足度の向上に繋がります。
常に顧客の視点に立ち、競合との差別化を意識したDXの展開を目指しましょう。
建設DXの取り組み事例
清水建設
清水建設は、建設現場の管理を画期的に変革する「Shimz AR Eye」というシステムを導入し、業界内での注目を集めています。
このシステムは、AR(拡張現実)技術を駆使し、タブレット端末を通じて、建物の3Dモデルデータ(BIMデータ)と現実の映像を融合させることで、施工現場の管理を効率化します。
これにより、従来は手間がかかっていた建設現場の躯体や設備配管の確認作業が簡素化され、現場作業の負担軽減に大いに貢献しています。
Shimz AR Eyeの具体的な利点
Shimz AR Eyeの導入により、現場作業者はタブレットを使って、直感的に建物の各部を確認できるようになりました。
BIMデータと現実の映像が自動的に重ね合わされるため、施工の精度向上やエラーの早期発見が容易になるなど、施工管理の効率化が図られています。
清水建設のDX事例
清水建設は、「DX銘柄2021」および「DX銘柄2022」として選出され、さらに経済産業省による「DX認定取得事業者」にも選ばれるなど、建設業界におけるDXの先駆者として高い評価を受けています。
これは、同社が伝統的な建設技術にデジタル技術を組み合わせた取り組みを積極的に進めていることに起因します。
清水建設のDX戦略の内容
同社のDX戦略は、コンピュテーショナルデザインの活用やBIMデータの連携、さらにはロボットや3Dプリンタの現場導入に及んでいます。
また、AR技術を活用した施工管理や、3Dプリンタによるコンクリート柱の構築、自律型溶接ロボットの活用など、次世代技術の積極的な導入により、建設現場の効率化と革新を実現しています。
DX-Coreの開発
清水建設は、建物運用のデジタルプラットフォーム「DX-Core」を開発し、このプラットフォームにより建物運用管理の効率化と利用者の利便性・安全性の向上を図っています。
エレベーターや監視カメラ、各種IoTデバイスとの連携により、建物運用の革新を進めており、これらの技術を顧客向けに商品化し、実装提案も行っています。
戸田建設
戸田建設株式会社は、デジタル技術を駆使した社会活動の革新に取り組んでいます。
同社では、デジタル化により生まれる相互連携のエコシステムを利用し、新たな価値創造を目指しており、これにより事業の拡大と深化が図られています。
具体的には、価値あるデータの収集とその活用、そして、他のプラットフォームやエコシステムとの連携がその核をなしています。
戸田建設のDXの利点
戸田建設はデジタルトランスフォーメーション(DX)において、BIM/CIMを中心とした「ものづくりのデジタル化」を進めています。
このアプローチにより、建設業界における生産システムの効率化と高度化が可能になっており、新規ビジネスへの挑戦にも積極的です。
戸田建設のDX事例
戸田建設は、DXを通じて新たなサービスの提供に成功し、これにより高品質なサービス提供が可能となりました。
例えば、病院施設や公共インフラにおけるデータ収集と分析により、施設企画や高度な行政サービスの提供が実現しています。
また、高齢化社会や公共インフラの老朽化といった現代の課題に対しても、DXを活用して効果的な解決策を提供しています。
戸田建設のDX戦略の内容
戸田建設のDX戦略は、4つの主要アクションに分かれたロードマップに基づいており、具体的にはプロジェクト参画型組織体制の確立や、ICT統轄部による「DX推進室」の設置が含まれます。
これにより、建築、土木、設計、価値創造の部門間での情報連携が強化され、DXの推進が図られています。
さらに、社員のデジタルスキル向上のためのリカレント教育や社外サービスのオンライン学習プラットフォームの活用など、継続的なデジタル人財の育成にも力を入れています。
鹿島建設
鹿島建設株式会社は、デジタルトランスフォーメーションを進める上で「人」を中心に据えたアプローチを取っています。
企業内でのデジタルリテラシーの向上に力を入れ、全社的な取り組みを実施しています。
その結果、「人に焦点を当てた持続可能な都市開発」の実現を目指しています。
この取り組みは、建設業界におけるDXの成功例として広く認識されています。
鹿島建設のDXの利点
鹿島建設のデジタルトランスフォーメーションの進展は、建設プロセスの効率化や新たな価値の創出において顕著です。
スマートビルやスマートシティの構築、デジタルツインの活用、VR技術の導入など、革新的なデジタル技術の積極的な採用が進んでいます。
また、ソフトバンクグループとの協業による四足歩行ロボット「Spot」を用いた実証実験にも成功し、業界内での評価が高まっています。
鹿島建設のDX事例
鹿島建設は、デジタル社会の進展に伴い、顧客と社会が直面する新たな課題に対応するため、デジタル技術を駆使して
「中核事業の強化」
「新たな価値創出」
「経営基盤整備」
の3つの領域でDXを推進しています。
その結果、社会に対する豊かで活力ある世界創りに貢献していると評価されています。
鹿島建設のDX戦略の内容
鹿島建設は、DX戦略を2つのカテゴリーに分けて展開しています。
「既存事業や経営基盤の強化(DX1.0)」と「事業領域の拡大・新たな収益源の確立(DX2.0)」です。
前者では、建設生産のプロセス変革を通じた生産性の向上や魅力の強化に焦点を当て、後者ではデジタル技術を活用して新たな市場領域の拡大を目指しています。
これらの施策の基盤となるのが、デジタル化の推進です。
現在、鹿島建設はDXの初期段階に位置しており、今後の取り組みが企業競争力に大きく影響を与えるとされています。
平山建設
平山建設は、効率的で魅力的な職場環境を目指して、中小規模の企業にも実現可能なデジタル変革を進めています。
コミュニケーションツールの活用やクラウドストレージへの書類管理移行がその主な施策です。
これにより、電話や移動の手間、コミュニケーションミスに起因する仕事の手戻りを大幅に削減し、効率化を実現しています。
平山建設のDXの利点
平山建設のDX導入は、特に文書や写真のデジタル化により、記録の明確化と後の確認作業の容易化に貢献しています。
これにより、協力業者とのデータ共有も円滑化され、生産性の向上に繋がっています。
また、社員教育にも注力し、DXツールの効果的な活用を促進しています。
平山建設のDX事例
建設業界での人手不足や高齢化といった課題に直面する中で、平山建設はDXを通じてこれらの問題に対処しています。
特に、地域建設会社との協力によるDXモデルの構築は、業界全体における理想的な事例となっています。
平山建設のDX戦略の内容
平山建設では、建設現場における業務効率化のために「現場サイト」というDXツールを導入しています。
このツールは、工程表や図面などの情報をクラウド上で共有し、現場作業の効率化を図るものです。
また、ネクストフィールドおよびNTT東日本と連携し、ダッシュボードサービスやボイスKYシステムを活用することで、安全性の向上や働き方改革の推進を目指しています。
これらの施策は、2023年から2024年にかけて具体的に実施される予定です。
後藤組
後藤組は、建設業界のデジタル化トレンドを先導しており、労働力不足という課題に対応するため、デジタルツールの導入を積極的に進めています。
この動きは、業界内での効率化と市場の新たな付加価値の創出を目指すものです。
具体的には、デジタル技術を駆使して業務のやり方を変革し、2025年のデジタル環境問題にも対応しています。
後藤組のDXの利点
後藤組のDX戦略は、既存のビジネスプロセスをデジタル化し、生産性を向上させることに重点を置いています。
データを活用して顧客に新しい価値を提供し、競争上の優位性を確立することが主な目標です。
後藤組のDX事例
後藤組のDX取り組みは、業界においてモデルケースとして高く評価されています。
特に、デジタルツールの活用による生産性の改善や、データ駆動型の経営による競争力の強化が注目されています。
後藤組のDX内容
後藤組は、DXを推進するためにいくつかの重要なプロジェクトを実行しています。
これには、SaaSの活用、リアルタイム経営、バックオフィスの業務効率化、組織体制の変革、次世代型建設DXの推進、内製的IT人材の育成などが含まれます。
これらの施策は、組織内のデジタル環境のブラックボックス化を防ぎ、長期的な視点でデジタル環境を構築することを目的としています。
熊谷組
熊谷組はダム建設における革新的なステレオカメラ技術を導入し、コンクリート製造に必要な大粒骨材の選別を自動化しました。
この技術は、トラックに積載された骨材を立体的に撮影し、データ化することで粒径を正確に判別します。
こうした施工管理の効率化により、ダムコンクリートの製造をスムーズに行い、人的ミスのリスクを大幅に減らしました。
熊谷組のDXの利点
熊谷組のDX取り組みは、2019年の「DX元年」宣言以来、土木事業の情報化施工やBIMの活用など、建築業界におけるデジタル技術の先駆者として注目されています。
無人化施工の推進や自動化技術の導入は、生産性の向上だけでなく、労働環境の改善にも寄与しています。
熊谷組のDX事例
熊谷組は、経済産業省から「DX認定事業者」として認定され、業界内で高い評価を受けています。
この認定は、デジタル技術を経営に取り入れ、DX推進に積極的に取り組んでいる企業に与えられるもので、熊谷組のDX戦略が業界内で模範とされています。
熊谷組のDX戦略
熊谷組のDX戦略は、全社員のデジタルリテラシーの向上、データサイエンティストの確保、そしてデジタルプラットフォームの構築に重点を置いています。
2023年度には、全社員を対象にDX教育を実施し、データドリブンな経営を目指します。
また、新たな基幹システム「建設WAO」の導入や、ICTツールの活用による生産性向上が進められています。
これらの取り組みは、デジタル技術を活かした事業革新として位置づけられ、熊谷組のDX推進の鍵を握っています。
| 企業名 | 取り組み概要 | 特筆点 |
|---|---|---|
| 清水建設 | デジタル技術の積極的な導入で建設業の生産性向上を図る | 技術革新を通じた建設業のモダナイズ |
| 鹿島建設 | DX認定取得、四足歩行型ロボットの実証実験など先進技術活用 | 革新的ロボット技術の実地テスト |
| 後藤組 | リアルタイム経営とデータドリブンアプローチによる効率化 | 労働生産性の向上に注力 |
| 竹中工務店 | 先進的な建設技術の開発・導入で業務の効率化を推進 | 建設技術の革新をリード |
| 平山建設 | スモールDXによる業務効率化、クラウドベースのツール導入 | 中小規模事業者向けDXの模範 |
| 戸田建設 | 総合的なDX戦略の展開、ビジネスプロセスのデジタル化 | 組織全体でのDX推進 |
まとめ
建設業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、単にテクノロジーの導入以上の意義を持っています。
業界全体が直面する労働力不足や生産性の問題に対応するため、清水建設、鹿島建設、後藤組、平山建設、戸田建設といった主要企業は、DXを戦略的に活用しています。
これらの企業は、デジタル技術を利用して業務プロセスを最適化し、効率的な施工を実現することで、建設業界の課題に積極的に取り組んでいます。
例えば、鹿島建設のようにロボット技術を実験的に導入する企業もあれば、平山建設のようにスモールDXを推進して中小規模事業者にも適用可能なモデルを開発する企業もあります。
これらの取り組みは、業界におけるDXの重要性と可能性を示しています。
各社のDX戦略は、建設業界の生産性向上、作業の効率化、そして長期的な持続可能性を目指しており、これからの建設業界を形作る重要な要素となっていることは間違いないでしょう。
RELATED
関連記事

人手不足とコスト上昇の課題を解決する「ロボット×IoT」サービス:『サビロボ』

求人掲載がスムーズに!現場を助ける新しい方法とは