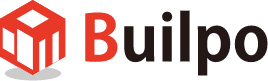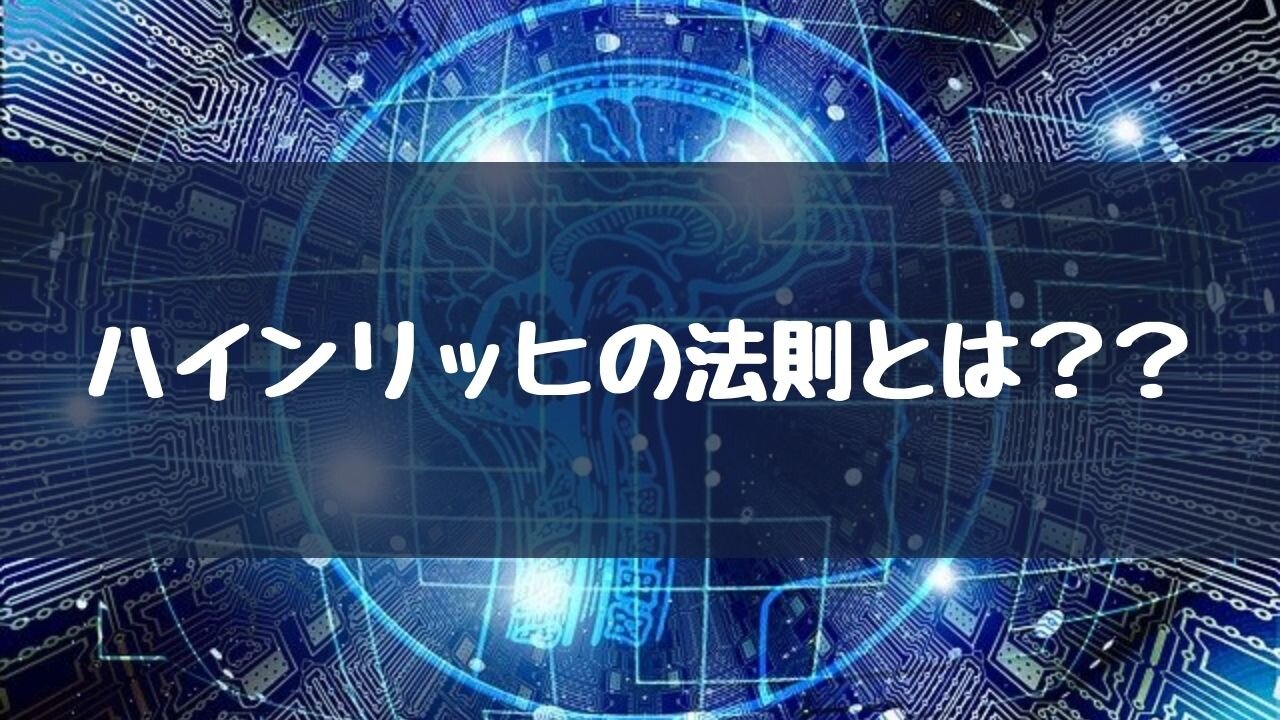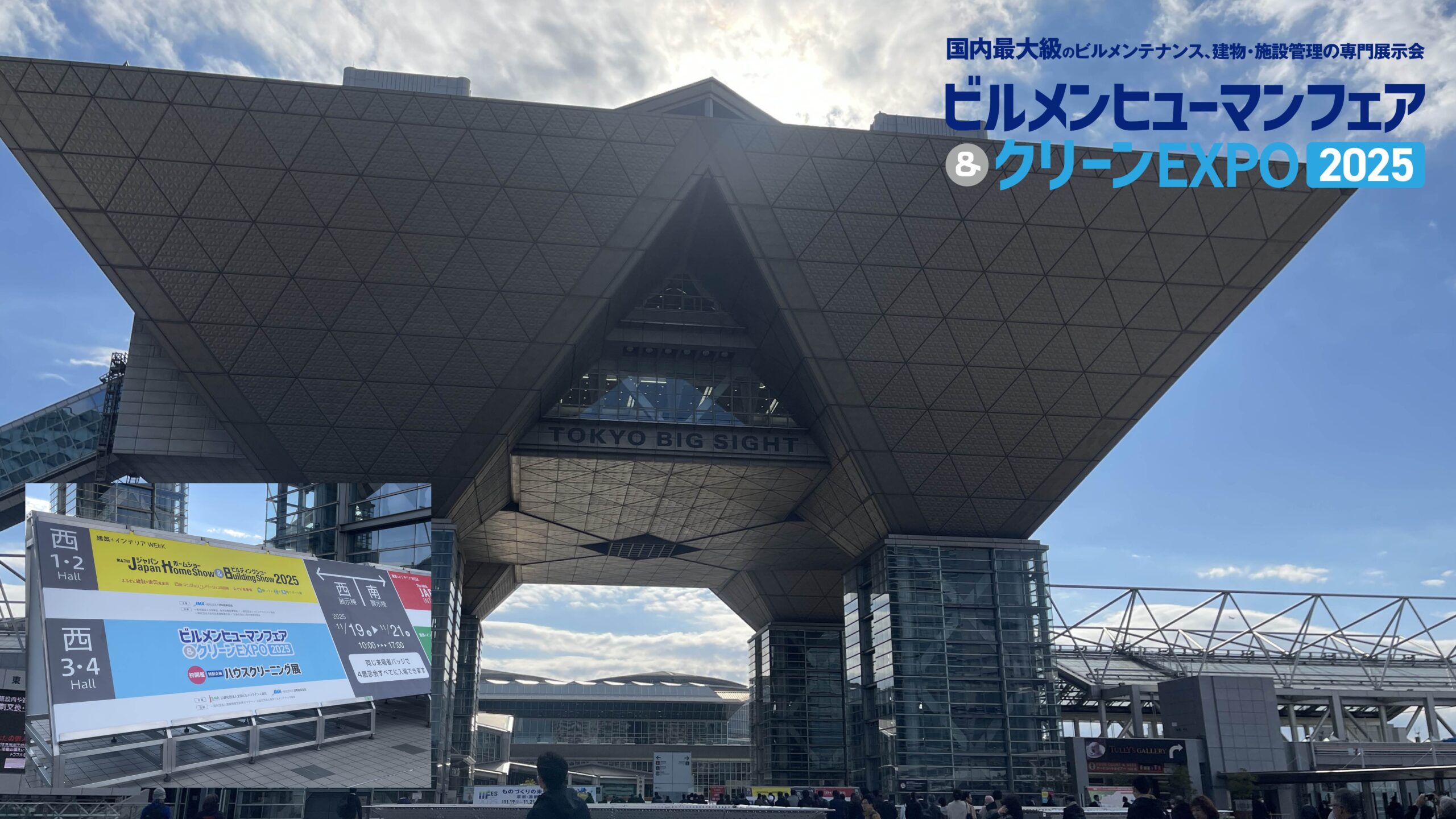『わかりやすく』ハインリッヒの法則とは何?具体例を用いて解説
ハインリッヒの法則とは、
「重大な怪我につながる事故1件の背後には29件の軽事故があり、さらにその背景に300件のヒヤリハットがある」
という労働災害における怪我の回数を分析した法則です。 その比率から1:29:300の法則と呼ばれることもあります。
わかりやすくハインリッヒの法則とは?
ハインリッヒの法則とは、1920年代アメリカの損害保険会社で働いていた ハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが見つけ出した法則のひとつです。
5000件以上の労働災害による怪我を調査した結果つきとめた経験則で、
『重大な産業事故は偶然ではなく、事故が起こるまでに何かしらの予兆があり防ぐことができる』
という教訓を統計学的に解明しました。
簡単に説明すると、Aさんがある仕事で事故を起こし重傷を負った場合、統計学的には、Aさんは重症事故以前にその仕事で同様の事故を329回起こし、そのうちの300回は無傷、29回軽い怪我をした、という事になる…
というのがハインリッヒの法則です。
つまり、軽症だった29回と怪我に至らなかった300回の事故を調査し、日常的な軽事故自体をを未然に防ぐことが、重大な事故を防ぐ方法だ、ということですね。
ハインリッヒの法則の具体例
ビルメンにおける重大事故もハインリッヒの法則で防げると言われています。 例えば以下のような労働災害事例があります。
「脚立をハシゴ状に伸ばして使用し、2階の窓清掃を行なっていたところ、はしごの上2段目から転落し複雑骨折をした。」 高い位置の窓清掃は、ビルメンに従事していれば、よくある仕事内容ですよね。
この重大事故にはどのようなヒヤリハットが隠れていたと想像できますか?
「脚立の上で足が滑る」「脚立がずれる」
などが容易に想像できますね。
これらが「怪我に至らなかった300回の事故」に相当します。
また、
「脚立を押さえている人がおらず、やむなく一人で使用したら倒れて膝を打撲した」
こんな経験をしたことがあるかたもいらっしゃると思います。
一歩間違えれば重大な事故につながるかなり危険な事故ですね。
これがハインリッヒの法則における「29件の軽事故」です。
脚立使用時のヒヤリハットや軽事故を思い返し、それぞれ
「靴が滑らないようにする」「一人で脚立を使用しない」
などの対策をとることで、重大事故の防止につながるのです。
ハインリッヒの法則が古いと言われるのはなぜ?
ハインリッヒの法則は、1931年にアメリカで発表されました。
90年以上前、つまり戦前のアメリカの労働事故を分析した経験則だということです。
それから100年近くたった今、危険な現場はかなり改善されましたし、命が危険にさらされるような危険な仕事の多く機械がこなしてくれるようになりました。
そこから、ハインリッヒの法則はもう古いのではないか、と言われるようになったようです。
しかし、働き方が変わっても労働災害は未だ起きているのが事実です。
ほとんどの大型機械は取り扱いを間違えれば重大な事故に繋がります。
電気や水、火の取り扱いに細心の注意が必要なのも昔と変わりません。
つまり、ハインリッヒの法則が発見された時と現代では、働く状況は変わっていても、重大な事故が起こる背景はほとんど変わりないと言えるのです。
ハインリッヒの法則のまとめ
ハインリッヒの法則は、私達が怪我をせず働く為に必要な法則だということがわかりましたね。
ヒヤっとするような現場を見つけたら、周りや上の人に報告することで労働災害を未然に防ぐことができます。
日々のヒヤリハットを見過ごさず、怪我なく安全に働ける現場を作りましょう。
RELATED
関連記事

人手不足とコスト上昇の課題を解決する「ロボット×IoT」サービス:『サビロボ』

求人掲載がスムーズに!現場を助ける新しい方法とは