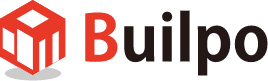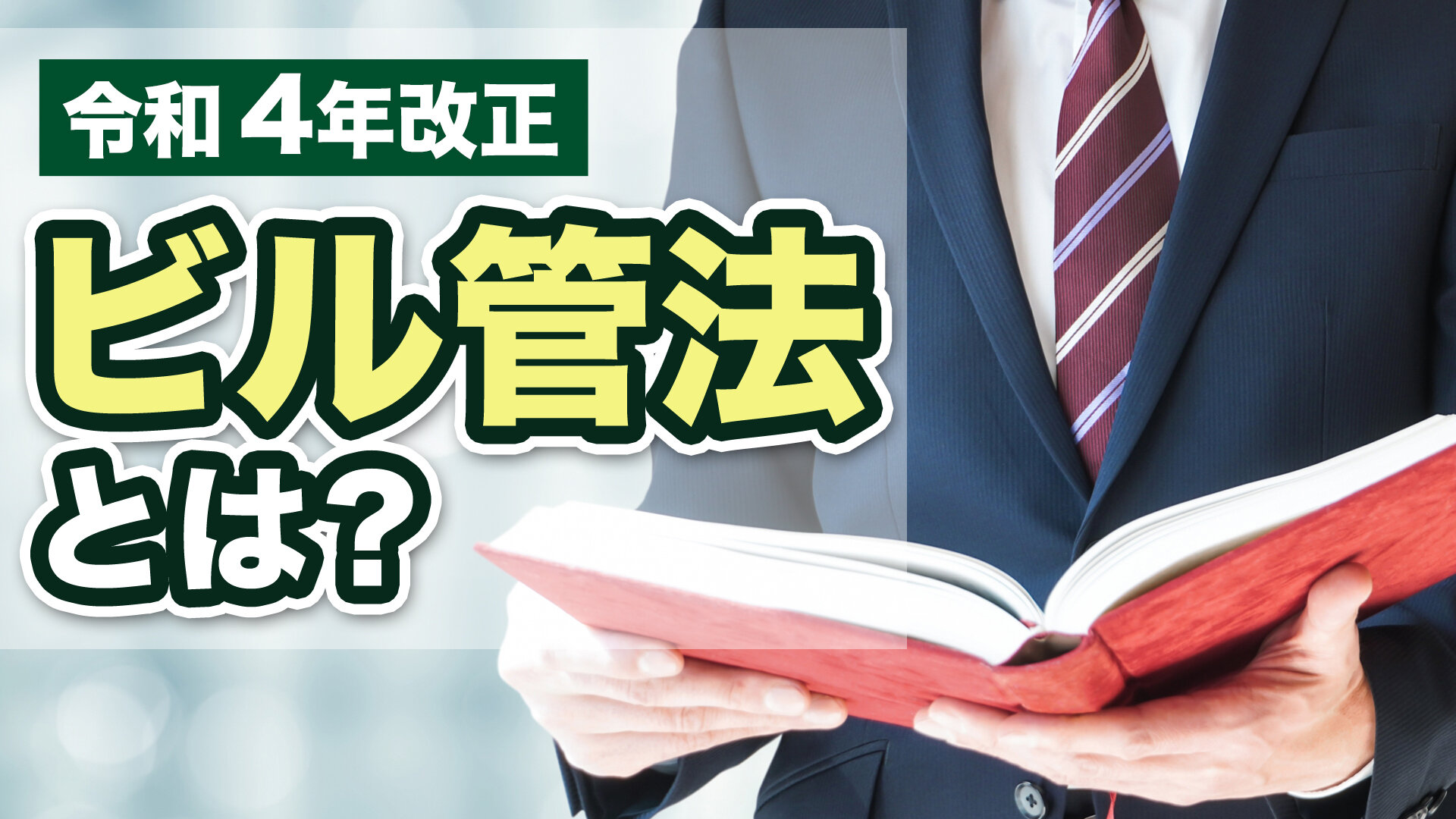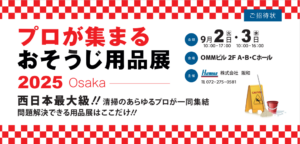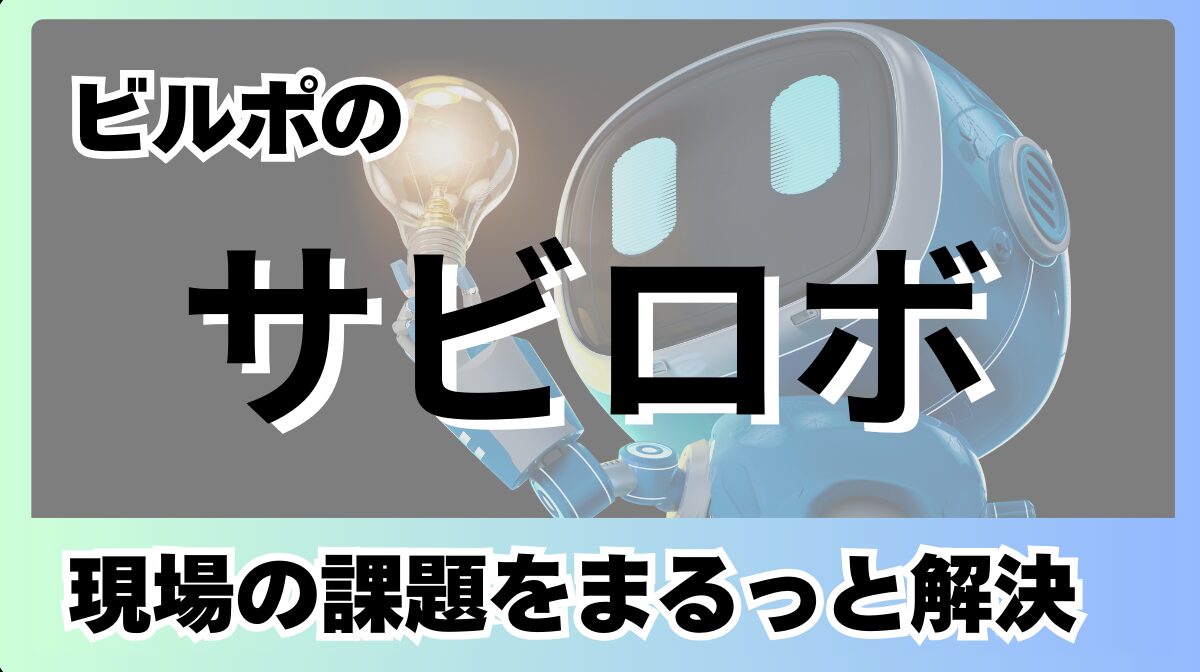本記事では「ビル管法」に関して、法律の詳細・対象となる建築物・点検項目・令和4年に行われた制度改正に焦点を当てて解説していきます。
ビル管法を順守した施設の運営で「テナントの入居率を上げたい」「テナント企業の入居期間を伸ばしたい」とお考えのオーナー様は、ぜひご覧ください。
ビル管法とは
ビル管法とは、不特定多数の人が利用する施設(ビルや商業施設など)の維持管理について、環境衛生の観点から確認が必要な事項を定めた法律です。
ビルの経営やビルの管理をするうえで、避けては通れない法律・制度であるため、ビル管理業の中で最も基本的な法律とされています。
正式名称
ビル管法は業界で良く使用される通称で、正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。主にビルを管理する法律であることから、ビル管法と略されます。
他にも「ビル管理法」「ビル衛生管理法」「建築物衛生法」などといった呼び方もあります。企業や業界によって呼び方が変わるので、それぞれを認識しておきましょう。
※本記事では、最も業界で使用される「ビル管法」に統一して解説を続けます。
目的
ビル管法の目的は、オフィスビルなどの大規模な建築物の衛生環境の悪化を防止・抑制し、安全管理を推進することです。
制定は1970年(昭和45年)、高度経済成長の終盤に該当する時期です。日本の発展に伴い高層ビルが急速に増加、同時に建築物内の衛生管理が重要だと認識されはじめます。
そこで衛生管理を目的とするビル管法が制定されました。
責任を負う者
ビル管法の各種管理の義務を負うのは、
①建築物の所有者
②建築物を借りて使用している人/会社
③建築物の管理を委任されている人
です。
建築物に常駐している必要はなく、あくまで所有権または管理権限を有する人/会社が対象となっています。

ビル管法の対象建築物
ビル管法の対象となる特定建築物とは、用途と施設の規模によって定義されています。
▼特定建築物の定義
①建築基準法に定義された建築物であること
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館。
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
引用:厚生労働省
用途による定義は②にあたり、該当するのは商業施設、娯楽施設、美術館、ホテル、オフィスビル、事務所、学校など様々です。
③にあたる施設の規模は、上記用途に使用される面積のことを指し、3000㎡以上であることが特定建築物の定義です。
このうち、オフィスビルなどの「事務所」の数が最も多く、令和2年の時点で19,302棟が該当しています。
次に多いのは商業施設や娯楽施設を含む「店舗」で10,144棟、全ての特定建築物を合わせると47,273棟です。
特定建築物の届け出ルール
特定建築物に該当する建築物を所有または管理し始めた場合、ビル管法に則って1ヶ月以内に各都道府県知事(保健所)に届け出をしなければなりません。
この際、「建築物環境衛生管理技術者免状」という国家資格を有するビル管理士(ビル管理技術者)を1人以上選任し、その氏名を記載して提出する必要があります。
また、特定建築物の用途や面積など届出内容に変更があった場合にも、1か月以内に届け出が必要です。こちらは、特定建築物が何らかの理由で定義から外れ、特定建築物ではなくなった場合も同様です。

ビル管法の点検項目
ビル管法で点検する項目は、以下の4つです。
・水質検査
・空気環境測定
・衛生管理
・清掃
それぞれ詳細に見ていきましょう。
水質検査
水質検査は、ビル内で使用される飲料水・雑用水・排水に関して定期点検を行います。
もし測定値が基準に満たない場合は、給水設備の清掃などで基準値を満たすための改善が必要となります。
検査および清掃は、専門業者に依頼することがおすすめです。
各都道府県のホームページでは、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」の登録業者も掲載されているので、そちらからチェックしたうえで依頼しましょう。
空気環境測定
空気環境は、空調設備を有するビル管理者を対象に定期的な測定を義務付けています。機械換気設備があるビルに関しては、温度と相対湿度の基準が適用できないので、測定は不要です。
もし測定値が基準に満たない場合は、空調設備の改善などで基準値を満たすための改善が必要となります。
こちらも水質検査と同様に、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」の登録業者に検査および清掃を依頼するのがおすすめです。
衛生管理
衛生管理とは、害獣・害虫の発生予防や駆除作業のことを指します。
大規模な施設には、ヒトの健康を害する可能性のある害獣(ネズミなど)や、害虫(ゴキブリやハエなど)が住みつきやすいです。それらの発生場所を特定し、予防および駆除を行わなければなりません。こちらは6ヶ月に1回の実施が必要です。
確実に予防・駆除を行うためには、薬事法の規定による承認を受けた医薬品・医薬部外品を用いる必要もあります。
専門業者に依頼しましょう。
清掃
ビル内の清掃に関しては、日常的に行う「掃除」と、6ヶ月に1回行う「大掃除」があります。
「掃除」に関しては、日々の業務の中で行えるため業者に依頼する必要はないですが、「大掃除」に関しては大規模なものとなるため、専門業者に依頼するケース多いです。
こまめな掃除を心がけましょう。
令和4年4月の制度改正について
このようにビルの所有者・管理者にとって、欠かすことのできないビル管法ですが、時代の流れに沿ってその都度改正が行われてきました。そして、2022年(令和4年)4月にも、制度が改正されています。
改正の概要
改正の内容は以下の2点です。
①居室における建築物衛生環境基準に関して
・居室における一酸化炭素の含有率の基準について「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に見直す
・居室における温度の低温側の基準を「17度」から「18度」に見直す
②建築物環境衛生の管理技術者の選任に関して
・一つの特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除
・管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、(a)選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと、(b)選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、(a)と同様の確認を行うこと、(c) (a)及び(b)の確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
※引用:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の 公布について 厚生労働省 令和3年12月27日
改正の目的
今回の改正は、厚生労働省の建築物衛生管理に関する検討会での議論をもとに取りまとめられた「建築物衛生管理に関する検討会報告書」に基づいたものです。
近年発達したICTを踏まえ管理技術者選任に関する事項を見直すこと、国際基準などに基づいて見直しがされた「建築物環境衛生管理基準」の一部を修正すること、の2点を主な目的として改正されました。
近年の大気中における一酸化炭素の含有率が改善されていることや、ICTの登場で離れていても問題なくコミュニケーションがとれるようになったことなどが反映された、まさに時代の流れに沿った改正といえるでしょう。
ビルオーナーはビル管法の制度改正を理解しよう
ビル所有者および管理者は必ず知っておかなければならないビル管法。目的や点検項目、届け出ルールなどをきちんと把握し、遵守に努めるようにしましょう。
また、法律は時代の流れとともに改正を続けます。ビル管法も例外ではなく、2022年4月にも重要な改正が行われました。最新情報を把握するとともに、管理方法も新しい制度に沿ったものにアップデートしていきましょう。
▼参考URL
https://www.n-bunseki.co.jp/menu/water/drink
https://www.meccs.co.jp/column/50/
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hoken-chubu/eisei/kankyoeisei/22kentikubutu/kentiku.html”
https://bilumen-taishi.jp/building-pipe-law
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.subarusya-linkage.jp/img/b-template/jisha/download/p309.pdf”
▼引用
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
厚生労働省 令和3年12月27日
・引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html
RELATED
関連記事

人手不足とコスト上昇の課題を解決する「ロボット×IoT」サービス:『サビロボ』

求人掲載がスムーズに!現場を助ける新しい方法とは